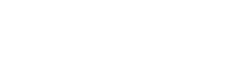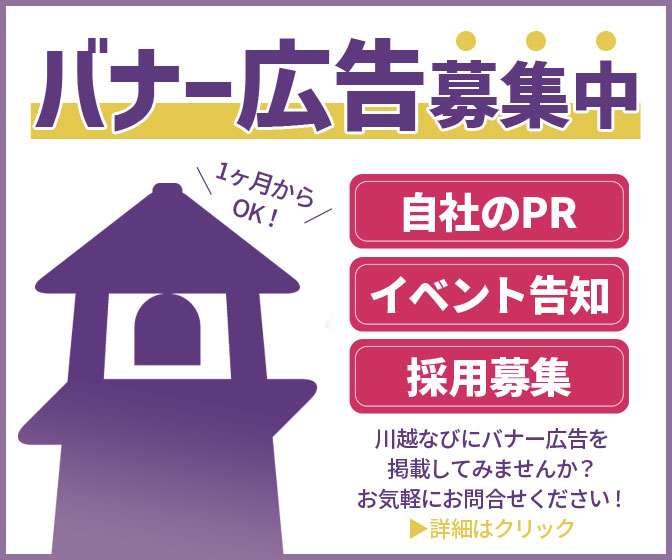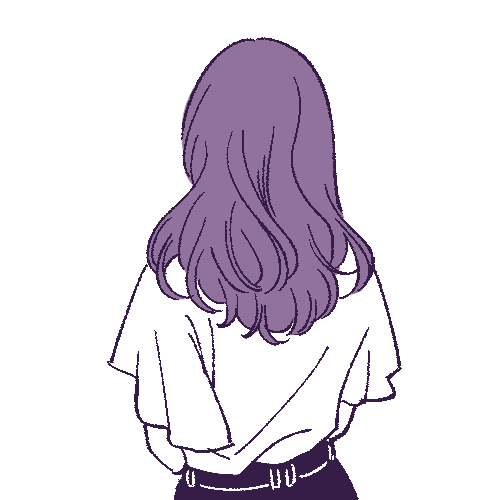この記事の目次
出世稲荷神社の由来・歴史
出世稲荷神社は、天保2年(1832年)地主である立川市が屋敷鎮守として京都伏見稲荷大社本宮より分社されたことに始まります。
稲荷神社はもともと農民による稲作や穀物の豊穣祈願の神として祀られ、大祭は毎年4月10日に行われています。
出世稲荷神社の御祭神・ご利益
出世稲荷神社の御祭神は
- 宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)
- 佐田彦之大神(さたひこのおおかみ)
- 大宮能売之大神(おおみやのめのおおかみ)
です。
中世から近世にかけて庶民に信仰が広まり、五穀豊穣だけでなく開運出世・進学・就職・良縁・安産などの様々な願い事を叶えてくれる神様として幅広く尊崇されています。
特に「出世稲荷神社」という名前が付いているということもあり、この神社に訪れた方は自身の立身栄達をお願いすることが多いです。
出世稲荷神社の見どころ
手水舎

鳥居から入ってすぐ左側に手水舎があります。
この手水舎には水道が付いており、手や口を清めることができます。
狛狐

本堂の手前にはお狐様が2体祀られています。真っ赤な前掛けが稲荷大明神の幟とマッチして可愛いです。

お狐様は玉と巻物をくわえており、それぞれ「知恵や稲荷の秘法」「稲荷大神の御神徳」を表しています。
本堂

出世稲荷神社の本堂です。
お賽銭箱は出ていませんが、扉に小さな穴が空いておりそこからお賽銭を入れることができます。
お参りの方法や神拝詞(となえことば)が掲示されていますので、ぜひ出世をお願いしてみましょう。
出世稲荷の大銀杏(大イチョウ)

出世稲荷神社には「出世稲荷の大銀杏」と呼ばれる2本の大きなイチョウの木があります。
このイチョウ達は、昭和33年3月6日に市指定記念物として認定されました。
大きく枝や葉を広げ、地中深くまで根を張っておりとても雄大です。
今回は初夏の撮影だったため葉が青々と茂っていますが、秋になると黄色く色づいて大変美しい姿を見せてくれます。

2本とも高さは約26.5メートルほどあり、向かって右側のイチョウは幹周り5.67メートル・根回り7.6メートル、左側のイチョウは幹周り7.25メートル・根回り9.7メートルととても大きな樹です。
樹齢は650年以上と推定されています。
600年前といえば室町時代ですね。 そんなときに芽を出したこのイチョウは、川越の町の変化をずっとと見ていたのでしょう。
第2次大戦中は、出征する人がこの神社にお参りをしてから行かれたそうです。
2021年の大イチョウの見頃は?

2021年11月25日に大イチョウを見に行ったところ、まだ緑の部分が多かったです。
日当たりの良い場所は少し黄色みを帯びていますが、見頃のピークはまだ先になりそうです。