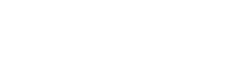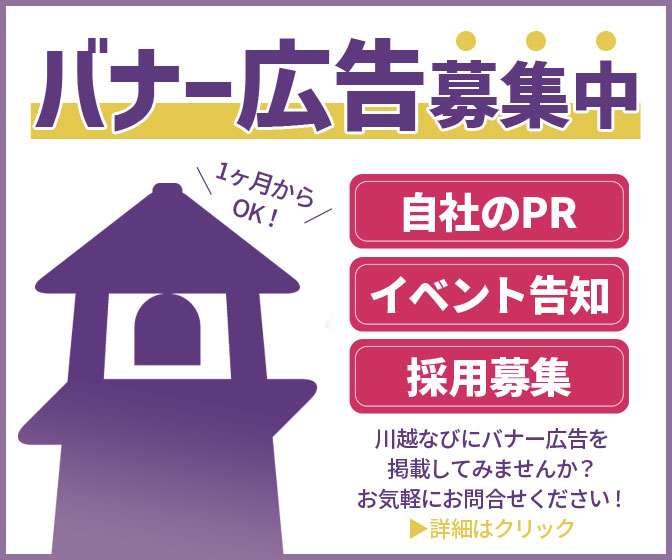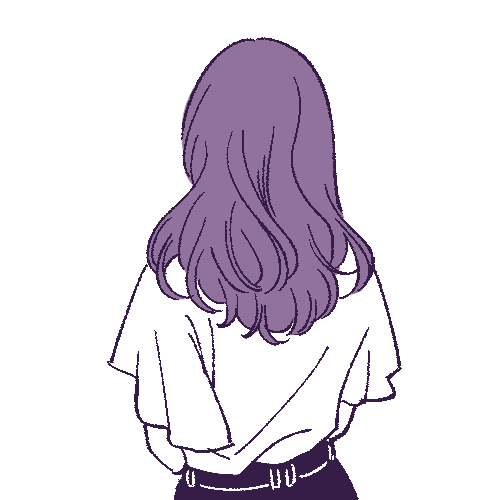この記事の目次
服部民俗資料館の歴史

服部家は文政5年(1822年)に、照降商(傘や下駄・草履を扱う問屋)として創業したことから始まります。
屋号を山新(山田屋・服部新助)といい、代々新助を襲名し、その商いを継いできました。
幕末には十組問屋(江戸に成立した同業者組合。株仲間のこと)の三番組照降仲間の年行事を務めます。
その後明治になっても、川越町外五ヶ村商人の公選により大行事の委嘱を受けることになります。
明治初期からは、薬種商(漢方薬等を販売する業種。現在は薬事法改正のため廃止)を兼業しています。
自家で薬を処方するほか、大阪や東京方面にも薬種問屋として漢方や洋薬を扱い続け、現在に至るということです。
服部民俗資料館の特徴

店舗部分は、江戸の様式を大いに残しているといわれています。
切妻(山形をした屋根形状の一種)、平入(屋根の流れ方向に扉がない建物のこと)、厨子二階(江戸から明治にかけて多く見られる古い様式)の構造を持つ塗家造りであるのが特徴です。
他にも、塗り込められた軒蛇腹、出梁、後方に棟が築かれ広がりのある瓦葺き(かわらぶき)であるところも当時の建築様式を感じさせます。
服部民俗資料館の入館料
服部民俗資料館の入館料は無料です。
館内は写真撮影ができないので注意してください。
服部民俗資料館のアクセス
服部民俗資料館のアクセス
fa-arrow-circle-right西武新宿線「本川越駅」徒歩13分
fa-arrow-circle-right東武東上線・JR埼京線「川越駅」徒歩23分
fa-arrow-circle-rightバス停「E14:蔵の街」徒歩2分