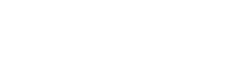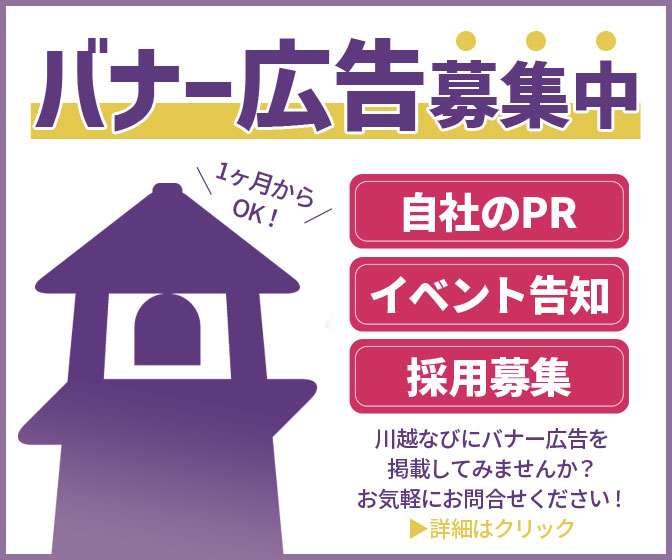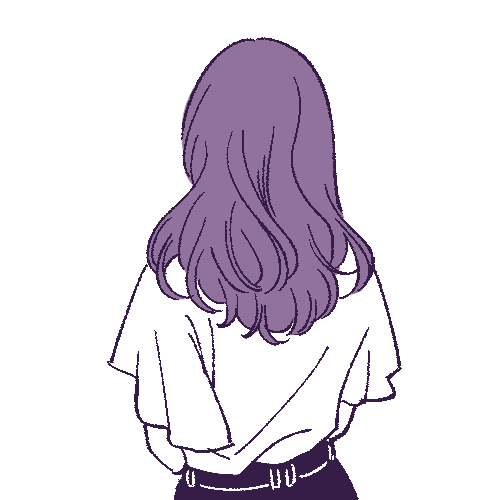この記事の目次
成田山のご本尊

成田山にはご本尊として不動明王が祀られています。
不動明王は仏教のさまざまな宗派から広く信仰されており、大日如来が姿を変えて現れた存在であるとも言われています。
また五大明王の中心となるのが不動明王で、成田山では本堂のご本尊に不動明王、その左右に四大明王が安置されています。
成田山のご利益
成田山のご本尊である不動明王には、厄除災難・現世利益・戦勝などのご利益があると言われています。
燃え盛る炎を背にして、右手に剣・左手に羂索(けんじゃく)を持ち、右目は天を向き左目は地を見ている天地眼という目を持つ姿が一般的ですよね。
サンスクリット語では不動明王のことを「アチャラナータ」と呼び、これには「動かざる守護神」という意味があります。
左手の羂索は、悪を縛るため、そして煩悩からなかなか抜け出せない人々を助けるための縄です。
不動明王は手に武器を持ち怒ったような勇ましい顔つきをしていますが、悪を断ち切って、どんな人でも正しい仏道に進むことができるよう導くためにこのような力強い姿をしています。
そんな不動明王を尊崇することによって煩悩が払われ、現世の苦難に立ち向かうことができるようになるでしょう。
川越七福神めぐり 第四番・恵比寿天
川越七福神めぐり第四番として、成田山には福の神の代表格である「恵比寿天」が祀られています。

もとは中国の神様が由来となっている七福神ですが、七人の神様の中で唯一の日本の神様が恵比寿天です。
狩衣と烏帽子(平安時代の貴族の服装)を着て、片方の手には鯛を抱え、もう片方の手には釣竿を持った恵比寿天の姿は知っている人も多いはず。

実は「恵比寿」という言葉には、外国人という意味があります。
もともとは遠い場所からやってきて人々に幸福をもたらす神様として、漁村では海の神様、山村では山の神様、または商人からは商売繁盛の神様など、さまざまな地域で多くの人々から信仰されてきました。
現在では五穀豊穣や大漁祈願はもちろん、商売繁盛・武運長久・除災招福など幅広いご利益が授かるといわれています。
成田山の見どころ
成田山の境内には、不動明王や恵比寿天にまつわるものはもちろん様々な見どころがあります。
ここでは、成田山に来たなら一度は見ておくべきスポットを全部ご紹介します。
内仏殿
1500体の不動明王や十二支の守り本尊としての八体仏などが安置されている建物です。
成田山川越別院が開創されてから150周年の2003年(平成15年)に、記念としてこの内仏殿を建てました。
本堂とは別に作られた内仏殿には、内仏殿のご本尊として木彫りの大日如来が祀られています。
大日如来を中心に信徒の方から奉納された木彫りの不動明王が500体、金色のプレートの不動明王が500体、銀色のプレートの不動明王が500体ずつ納められています。
また内仏殿の建物内には、八体仏という十二支の守り本尊も安置されています。
十二支の方角には八体の仏がいて、生まれの年のご本尊として守ってくれると言われています。
守り本尊願い札というものが一体500円で受付されているので、叶えたい願いを書いて本尊にお供えすることができます。
開山堂

成田山川越別院の開祖である石川照温上人が祀られているお堂で、ご尊像が置いてあります。
石川照温は一時、失明してしまいますが、お不動さまを厚く信仰し、ついには目が見えるようになりました。
そして現在では不動明王と石川照温にあやかり、開山堂には眼病平癒や視力回復を願う人々が多く訪れています。

お堂に掛けられている祈願のたくさんの「め」の絵馬も印象的です。
出世稲荷
合格成就や家内安全、開運成就などの願いを手助けしてくださるという出世稲荷のお堂があります。
この出世稲荷のお堂には、成田山川越別院の大本山成田山新勝寺のダキニ天を丁重に招きお祀りしています。
受験や試験を控えている人や一家の安全や健康を祈りたい人にぴったりです。
大師堂

平成27年に奉納された「大師堂」には、成田山新勝寺より勧請した宗祖弘法大師・興教大師・理源大師の三大師御尊像がお祀りされています。

また、成田山では開創160年記念事業の一環として、この大師堂を囲む形で四国八十八ヶ所霊場お砂踏の造営、霊場入口には「大五鈷杵」の設置も行われました。

五鈷杵は「ごこしょ」と読み、お大師さまが右手に持たれている密教の重要な宝具のことです。
設置されている五鈷杵は実際に触れられるので、お大師さまとの御縁を深められる大切なスポットです。

成田山の本堂にお参りした後はぜひ大師堂にも立ち寄ってみてください。
福寿殿

小江戸川越七福神めぐりの第四番である恵比寿天をお祀りしているお堂が福寿殿です。
商売繁昌や社運隆昌から福に関わる願いを叶えてくれると言われています。
七福神めぐりの際はぜひ、このお堂に祀られている恵比寿さまの尊像の前で手を合わせたいものです。
また、本堂の右側には「縁結七福弁才天」が祀られています。
お堂の下には「恋みくじ結び所」があるので、恋のおみくじはここに結びつけてくださいね。
水掛不動尊

「縁結七福弁才天」の隣には「水掛不動尊」があります。
水を掛けながら願を掛けることによって人々の願いを叶えてくれるといわれています。
また、不動明王は密教における最高位である大日如来の化身であり、迷いを断ち切り正しい仏の道へと導いてくれる存在です。
現世利益を与えてくれる仏さまとしても知られているため、煩悩退散や厄除け、学業成就などをお願いする方が多いです。
200匹の亀の池

境内には200匹以上の亀が住む亀の池があります。
橋の上から池を覗いてみると水際のあたりにたくさんの亀が集まっていました。
動きが緩慢なので目立たないのですが、よく観察するとあちこちに甲羅干しをする姿を見ることができます。

池がいつからあるのかは不明ですが、捕まえられた生き物を仏教の慈悲の心により解き放つことを目的とした放生池として地域の人々に親しまれているそうです。
冬は冬眠に入ってしまうためその姿を見ることはできませんが、暖かい時期には親亀、子亀、そして孫亀まで一緒にいる姿を見ることができます。
水琴窟

成田山には「小江戸川越七つの音風景」に選ばれた水琴窟があります。
この水琴窟は置型のもので、庭にかめを埋めることなく音色を楽しめます。
耳を近づけてみると、琴のような軽やかな音色が聞こえてきました。
成田山に来た際はぜひこの水琴窟で風景だけでなく音も楽しんでみてくださいね。
秋の七草・撫子
成田山川越別院の秋の七草は撫子です。
恵比寿天が祀られている福寿殿の前に植えられており、春と秋の2回、ピンク色の花を咲かせます。
成田山の授与品
成田山の御朱印
本堂の左側で御朱印やスタンプをいただくことができます。
成田山には、ご本尊の不動明王の御朱印や七福神の恵比寿天の御朱印など様々な御朱印があります。
そして関東三十六不動のひとつでもあるので、その28番の御朱印もあります。

また、令和5年(2023年)は弘法大師空海さまの生誕1250年を迎えるということで、生誕記念の一環として限定の御朱印がお授けされています。
通常はグリーンの御朱印ですが、限定デザインは赤に黒字で「弘法大師」と書かれており、とても格好いいデザインになっています。
こちらの限定御朱印は、24日御影供、28日の御縁日のみの授与です。
成田山の絵馬

成田山の絵馬は1つ500円で授与されています。
開山堂に祀る「め」の絵馬、不動明王、七福神の絵馬などがあります。
好きな絵馬を選んだら裏側にお願い事を書いてお祀りしましょう。
成田山のお守り
成田山のお守りは様々な種類があります。
健康長寿・必勝祈願・開運招福などの定番お守りはもちろん、二輪車に乗る方の安全を祈念したお守りやキャラクター付きのお守りなどバラエティに富んでいます。

基本的に授与品は受付で選ぶことができますが、境内にある「大師堂」の横には「八十八ヶ所お砂踏み御守」というお守りもあります。
弘法大師空海ご誕生1250年の記念もあり、お守りと祈願用の納札がセットになっています。
成田山「不動蚤の市」の様子
成田山の境内では毎月28日に「不動蚤の市」というフリーマーケットが行われます。
今回は、2021年6月に行われた蚤の市に行ってきました。

毎月28日には成田山の周りにオレンジ色ののぼりが飾られ、掘り出し物を探そうという人々で賑わいます。
門から一歩入るとたくさんのテントがあり、衣類・食器・置物・骨董品などの品々がずらりと並びます。

特に骨董品の種類はかなり多く、目利きの方は逸品を見つけられるのではないかとわくわくしてしまうのではないでしょうか。

筆者は骨董品は詳しくないのですが、レトロなグラスのセットや訳ありの着物などを眺めているだけでも楽しかったです。
もちろんお参りもできるので、お賽銭を入れてお願いをしてきました。
成田山の公共トイレ

成田山には、道路に面した場所に公共トイレが設置されています。
車イスマークの多目的トイレも併設されています。
成田山の駐車場

成田山には専用の駐車場が境内にあります。
Timesの有料駐車場となっており、駐車料金は60分220円です。